お葬式無料情報センター|大阪における葬儀、大阪のお葬式知識、大阪での葬儀社選びや大阪での葬儀の依頼方法について、正確な情報を無料で提供するサイト
- 葬儀社選びについて
- お葬式の金額について
- お葬式の品質について
- 互助会解約について
- 生活保護を受けている方のお葬式
- できる限りお金をかけずにお葬式を行いたい方
- 家族葬をしたいとお考えの方
- 自宅で家族葬を行いたい方
- 無宗教で行いたいとお考えの方
- 自宅に故人を連れて帰れない方
- お葬式はしなくていいとお考えの方
得する知識
念珠の選び方
昔、お釈迦様が、国中に疫病が流行って困っている波流離(はるり)国の王に「百八の木ケン子(もくけんし)の実をつないで、いつも手にして心から三宝(仏・法・僧)を唱えなさい。そうすれば煩悩が消え、災いもなくなります。心身も楽になるでしょう。」と語ったことが、『仏説木ケン子経』に説かれています。三宝は「南無帰依仏、南無帰依法、南無帰依僧」と称えることです。木ケン子(もくけんし)とは羽子板の羽根の重しになっている木の実のことです。
お釈迦様の教えが経典となって広く世間に流布するのは、お釈迦様が涅槃に入られてから五百年ほど経ってからですが、その間に念珠も数の概念や、一つひとつの玉に意味づけがされ、経典にも説かれて、仏教の法具として欠くべからざるものになっていきました。
仏教が朝鮮半島より伝来した時に、念珠も一緒に入ってきました。正倉院には、聖徳太子様が愛用された蜻蛉目(とんぼめ)金剛子の念珠や、聖武天皇の遺品である水晶と琥珀の念珠二連が現存しております。すなわち天平年間にはすでに念珠が伝わっていたことになります。それが仏具として一般の人々にも親しまれるようになったのは、鎌倉時代以降のことです。
数珠の玉の数はこの由来により108個が基本で、他にも半分の54個、4分の1の27個、10倍の1080個などがあります。
数珠にとって大切なのは珠の材質、房の材質、そして仕立てです。数珠の価格はこれらの要素によって決まります。
珠の材質には大別して水晶、メノウ、翡翠といった貴石(きせき)、菩提樹の実や蓮の実、桃の種といった木の実、黒檀・紫檀といった唐木材料、ガラス、樹脂製(プラスチック)に大別されます。また珊瑚・真珠も使われます。
このうち最も高価な素材は貴石類や珊瑚や真珠といった素材であり、宝石店でも扱われる材料です。ガラスや樹脂製品はあくまでも代用品です。商品名の頭にハリという言葉が付けられる時にはガラス製品であることが多く、新黒檀・新紫檀などという「新」の言葉が付けられる時には樹脂製品であることを示しています。
一生持つ物として考えれば、使うほどに手になじむので木の実を使った数珠をお勧めします。
房は正絹と人絹の二種類の素材が使われますが、正絹房が高級品であることは言うまでもありません。
また、数珠の形は宗派によって特徴のあるものですから、選ぶ時は、家の宗派を念頭に置いておくことが必要です。
お数珠の正しい持ち方は、座っているときは左手首にかけ、歩くときは左手に持ちます。
水引の表書き
お寺様への御礼
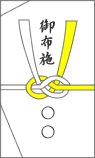 |
ご葬儀のとき ご葬儀のお礼は、正式には『御布施』と書きます。 |
 |
法事を営むとき 法事を営む場合、お寺様に読経いただくときのお礼は、すべて『○回忌法要御布施』とお書き下さい |
|
 |
新しくお仏壇を購入したと |
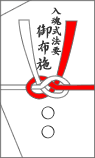 |
お墓を購入したとき |
|
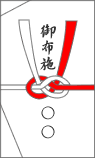 |
戒名(法名)を授与されたとき 生前中に戒名(法名)をいただいた場合、『御布施』と書きます。「位戒料・戒名料」でもよい。 |
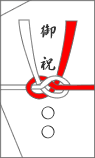 |
お寺様のお祝辞には |
|
 |
お性根を抜いていただくとき お仏像を修理するために、一時魂を抜いていただくときのお礼は、『撥遣法要 御布施』と書きます。ただし、浄土真宗では『遷仏(座)法要 御布施』と書きます。 |
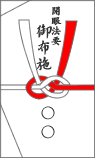 |
お性根を入れていただくとき |
ご葬儀に参列されるとき 宗派別の水引の書き方
 |
仏式のとき 表書きは「御香典・御香料」でも可。 |
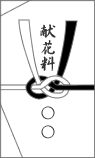 |
キリスト教のとき カトリック・プロテスタントも同じ |
|
 |
神式のとき 表書きは「御榊料・御神前」も可。 |
|
喪家へ訪問者するとき
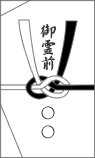 |
忌明(四十九日)までのご法事のとき 表書きは「御供」でも可。 |
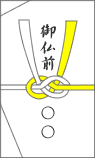 |
忌明(四十九日)後のご法事のとき 表書きは「御供」でも可。 |
|
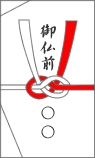 |
五十回忌・百回忌などの「弔い上げ」となるご法事のとき ■正式には赤白の水引を使用します。 |
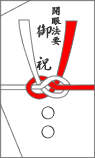 |
新しくお仏壇を購入された御家に御祝をするとき 表書き「入仏御祝」でもよい。 |
喪家より訪問者へ
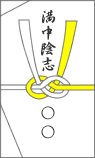 |
忌明(四十九日)のご法事のとき 引出物には『満中陰志』と書きます。 |
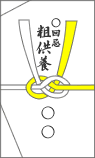 |
回忌法要のとき 翌年の一周忌から始まる回忌ごとの法要の時、引出物には『◎回忌 粗供養』と書きます。 |
|
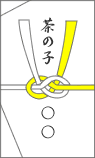 |
忌明(四十九日)のご法事のとき 供え物や配り物には『茶の子』(または粗供養)と書きます。 |
|
裏面の書き方
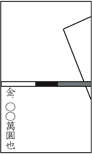 |
左下に、『金、○ ○ 萬圓也』と書きます。 |